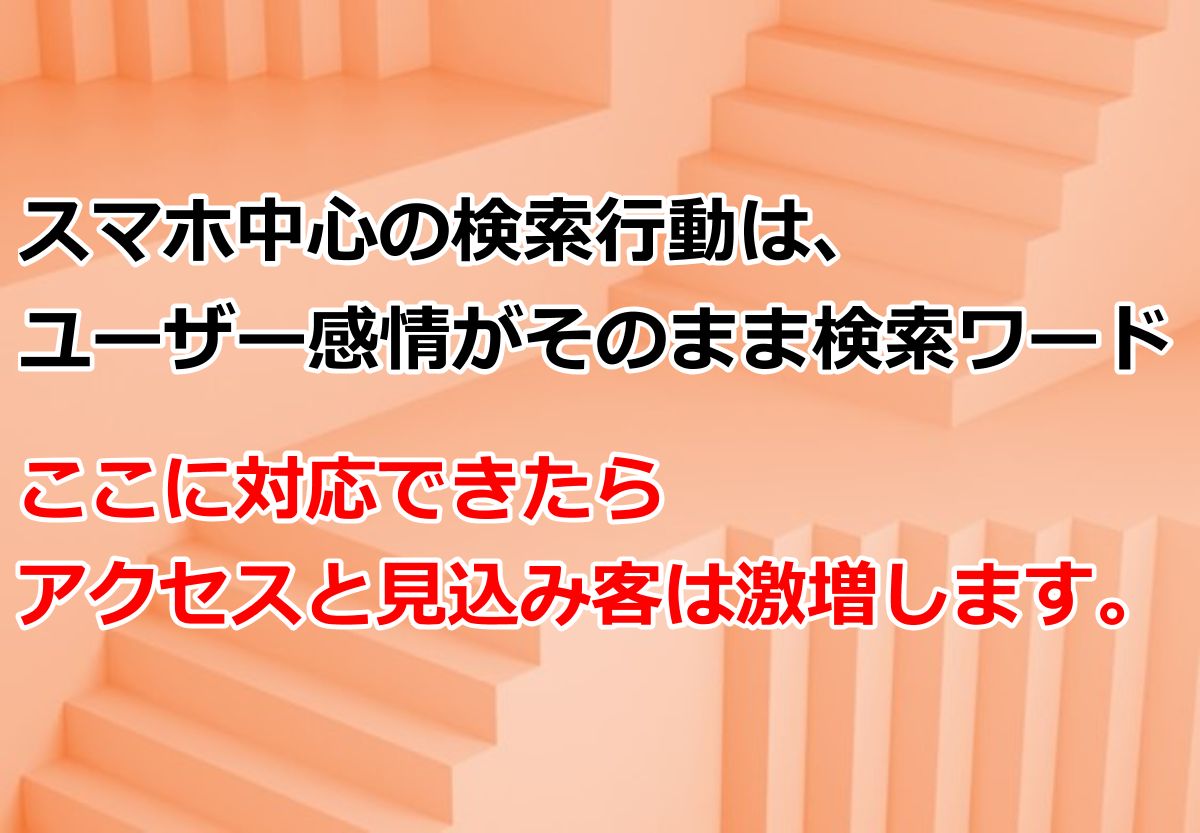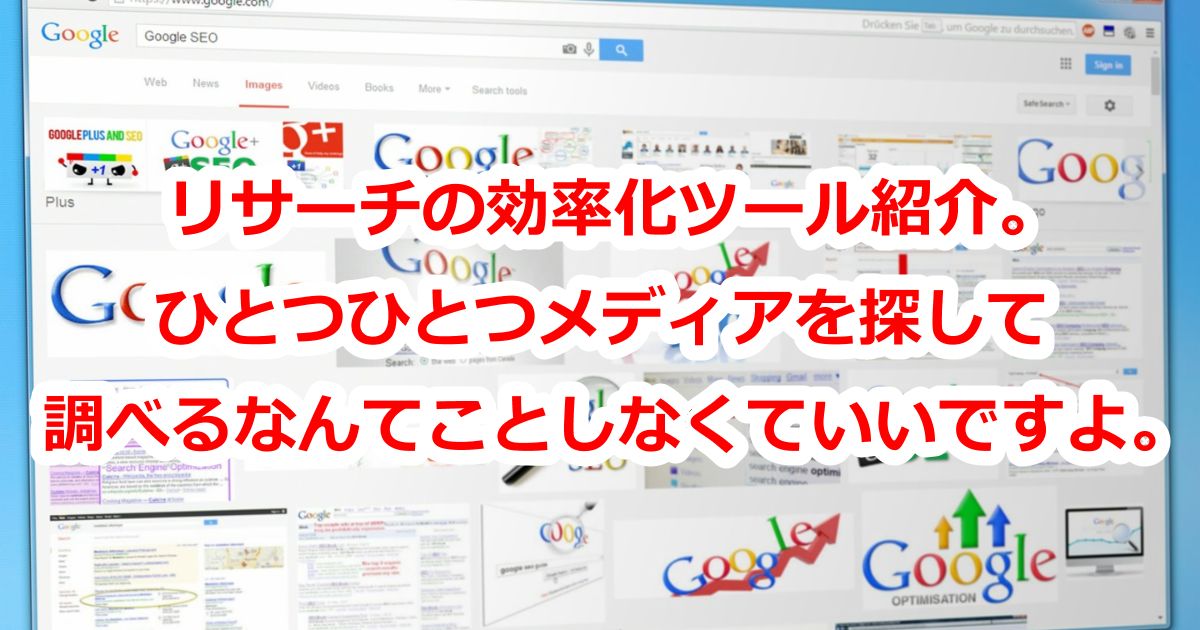広告運用セミナーを受けてきました。
広告には、Yahoo広告とかGoogle広告(検索広告と言われるもの)、Facebook広告とかTwitter広告などのSNS広告などいろいろな媒体があるわけですが、
内容は、現状の広告運用の最新の考え方、ノウハウ、いろいろな媒体における技術的な進化などについて学びました。
あと広告の概念において、広告運用はやり方だけ知っていてもだめでテクニックはその時の仕様によってもかわるので、広告や集客、ユーザー心理などと言った本質を抜きに考えるとうまくいかないということも。
これはビジネスにも通じるなと思いながらお話を聞きました。
広告に関してはユーザーが商品を購入する時の動線も多種多様になってきているので常にアップデートは必要です。
新しい手法は常に生まれますからそのテクノロジーをどう使うかは大事ですね。
でもこれも表面的なテクニックだけだとうまくいなかいんだろうと感じました。
【全体最適と部分最適】
そしてセミナーでもっとも共感できたのが、全体最適と部分最適という考え方。
お話し的には、広告運用を代理店に頼んだ場合にうまくいかないことが多いのはこの考え方の立ち位置ギャップ。
つまり依頼する側と依頼される側の立ち位置ですね。
例えばですが、代理店の仕事としてはどれくらいの費用でリストをどれくらい獲得できるかというのが仕事。
1リストあたりの単価を下げつつできるだけ多くのリストを集めるという、集客から販売までのフローで言えば「入口の部分」をやっている。
つまり全体の中でリストを獲得するという部分的なところですね。
しかしいくら安くしかもたくさんのリストが集まっても、例えばバックエンドの商材が売れないと意味がないわけです。
最終的に売り上げが上がらないといけないわけですね。
広告運用を依頼したとしても依頼者側は販売までの全体を見なければいけないわけですが、必ずしも代理店と共有で来ていないということも。
この立ち位置の違いで、
広告代理店は依頼された部分的なところに対して成果を出そうとする(広告の数字だけとか)部分最適という視点ですが、販売者側は売り上げというところまで見る全体最適という視点。
全体最適はビジネスモデルと全体の数字を把握するという考え方なので、たとえば購入しないリストを1件1000円で獲得するよりは、しっかり購入してくれるなら1件3000円でもいいわけです。
この考え方を明確にもち、共有できれば理想的ですね。
多分この部分最適と全体最適のギャップは、会社や大きくなってきた組織には発生しがちなものなのかな。